Latest topics 近況報告
たまに18歳未満の人や心臓の弱い人にはお勧めできない情報が含まれることもあるかもしれない、甘くなくて酸っぱくてしょっぱいチラシの裏。RSSによる簡単な更新情報を利用したりすると、ハッピーになるかも知れませんしそうでないかも知れません。
 の動向はもえじら組ブログで。
の動向はもえじら組ブログで。
宣伝。日経LinuxにてLinuxの基礎?を紹介する漫画「シス管系女子」を連載させていただいています。
以下の特設サイトにて、単行本まんがでわかるLinux シス管系女子の試し読みが可能!

コカコーラとiTunes - Aug 23, 2007
コーラに付いてるシールの裏の番号を特設サイトのフォームに入力するとiTunes Music Storeのタダ券が当たるというアレで3回ほど当たってるんだけど、欲しい曲がiTunes Music Storeに無いので使い道に困っている。
アイマスとかアニソンとかもっと充実しててくれればいいのに……
追記。さらに3回当たった……
執筆状況(漫画の) - Aug 15, 2007
宣伝エントリ書いた。
今週いっぱい夏休みを取って、先週土曜くらいから集中して作業に取りかかってます。ひとまず、最低ラインと考えていたギリギリの所はなんとかクリアした感じ。
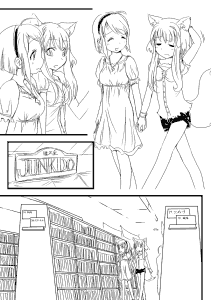
「ただお気に入りのキャラが出てきてヤッてるだけとかそんなんで百合を名乗るなボケカス」と直接言われたわけではありませんが、そういう言説を見て気になってしまったので、今回は頑張って日常の風景的な物を描こう、と思ってしまったが運の尽き。エロシーンだけだったら背景はシーツ一枚あればいいけど、日常となると町の風景とかあれこれ書かなきゃいけなくて死ねる しかもいぬくまさんのステキ漫画を見た後だと、話の幼稚さに顔から火が出る思いです。
いやまあ実際の所、とてもエロマンガなんか描いてられないよ的な精神状態だったからというのも理由の一つなんですけどね。
しかし、成人向けジャンルで申し込んでおきながら現状だとエロっちい要素が全然無いままなので、これから時間ギリギリまで粘って18禁なシーンを描こうと思います
自分が幸せかどうかと、好む作品の内容がハッピーかどうか - Aug 12, 2007
ケータイ小説の話を見てて思った事。
ハッピーエンドかアンハッピーエンドか。自分の人生がハッピーかアンハッピーか。よく、現実に満たされてない人ほどハッピーエンドの物語を好み、現実が満たされまくってて退屈で退屈でしょうがない人ほどアンハッピーエンドの物語を求める、という風な事を言うけれども、現実に対する代償として物語を消費する場合には、その説はよく当てはまる気がする。僕が今なんとかしてハッピーなお話を描こうと四苦八苦しているのも、何かを表現するためという事以前に、自分自身のための代償としての側面が強いと思う。
陰鬱なケータイ小説を好んで読む人達は、どうなんだろう。何を求めてそうしてるんだろう。
フォクすけぬいぐるみ - Aug 11, 2007
写真とラフと(壁紙とかの)イラストを見比べて、二次元と三次元はやっぱ違うんだねえとか、立体化する人のセンスが問われるんだなあとか、そんなことを思う。昨今の美少女フィギュアの質の向上はそういう意味でとても凄まじい。
試作品に「顔が鈴カステラ」とあるけど、最終完成品の正面顔もけっこう鈴カステラな気が……
まあ総じてこれはこれでイイ。個人的には一番最後の写真が愁いを帯びてて一番好きです。
SOI Asia + Mozilla = A+zilla らしい - Aug 08, 2007
たけんさんがとりあげてる、SOI A+zilla Add on Competition。プレゼン資料の一個目を見た人は気がついたかもだけど、これは僕が作った物だったりする。資料の内容自体はこないだのでぶこんの焼き直し(GomitaさんがSoftware Design誌の特集記事用に書かれたチュートリアルをベースにしたもの)で、150ページほどをImpressのプレゼンに手作業で変換するのに丸三日かかったと書いたのはこれのことなのでした。
いやね。こないだ慶應SFCまで行ってワークショップの先生のまねごとをやらせていただきまして。その時は事情を全然知らんかったのですが、こういうことだったんですね、と。
でぶこんの時はPC持ってきてる人が少なかったからチュートリアルをチュートリアルっぽく進めてよいものかどうか迷って悲惨な結果になったけど、この時のワークショップでは、それよりずっと少ない人数で全員それなりに基礎知識のある人ばかりだったんで、でぶこんの時にやりたかったことを実行することができたと思う。一人一人PCの画面を見て回って、うまくいってないようだったらアドバイスして、みたいな。
ただ、サンプルコードとか焦って用意したから全然テストしてなくて、それをダウンロードして使ってくれてた参加者の方が「うごかねえ!」とドツボにハマりまくっていたので、でぶこんの時とは別の意味で悲惨な結果になったと言えよう。最終的に予定の時間を大幅にオーバーしてたし……
ちなみに資料の英訳はボランティアかプロか知らないけど誰か他の人がやって下さいました。僕が訳したわけではないです。
ダイナミック疑似クラスに対応したよ(暫定) - Aug 07, 2007
テキストシャドウを:hover, :focus, :activeのダイナミック疑似クラスに対応させた……つもり。でも試してみたら:focusは意図通り動いてくれない。何でだろう。
userContent.css内でのtext-shadowの指定に対応したよ - Aug 06, 2007
テキストシャドウに、userContent.css内の指定を読む機能を加えた。圧倒的多数のサイトではtext-shadowはまだまだ使われていないけれども、ユーザースタイルシートを使えば色々遊べるよ、と。
といっても全サイトで同じ色の影しか指定できない、サイトごとにいちいち影の色を指定しなきゃいけない、なんてのじゃあとてもじゃないけど使ってらんないので、userContent.css内の指定のみ、色が無指定の時はCSS3の仕様を無視して自動的にそれっぽい影の色を適用するようにしてみた。例えばh1, h2, h3, h4, h5, h6 { text-shadow: 0.2em 0.2em 0.2em; }とかuserContent.cssに書いとけば、色んなサイトで影が付いて楽しくなるかもしれません。
ちなみに、XPCOMを使ってもuserChrome.cssやuserContent.cssから生成されたスタイルシートオブジェクトには絶対にアクセスできない。なので今回は、新規に空のドキュメントを生成し、そこにxml-stylesheet処理命令でuserContent.cssを読み込ませて、生成されたスタイルシートオブジェクトを参照する、という裏技を使っている。
Firefoxと少年ナイフ - Aug 06, 2007
Firefox Rock Festival '07のサイトに少年ナイフの名前が出ていて、一時期もてはやされたProxomitronが「少年ウェア」という謎ライセンスだったことを思い出してちょっと感慨深かった。ていうかProxomitron関係の話題で名前だけ知ってた。ギークにある意味馴染み深い名前だった「少年ナイフ」がギークに馴染み深いFirefoxとこうして同じ画面で名前を見ることになるとは、誰も想像だにしなかったに違いない。
公式サイト見てみたら、結成が1981年だそうで、僕の生まれる前からいる人達なんですね……
高橋メソッド in XULの改良 - Aug 06, 2007
LL魂で高橋メソッド in XUL RETURNSの問題点や課題がいくつか浮き彫りになったので、それへの対応をちょっとばかしやってみた。
- 高橋メソッド提唱者の高橋氏自身から「文字の大きさを変えられない」という指摘を受けたので、プレゼンデータ内に記述するコマンドで文字の大きさを変えられるようにした。
- 複数のファイルに別れているために導入に躓く人がいたので、スタイルシートも画像も全部takahashi.xulに埋め込むようにした。
- WYSIWYGに近くするための作業を開始。とりあえずソース表示だけじゃなく、ページごとにデータを切って表示できるようにしてみた。ページ単位の削除や編集の機能はあるけど、ページの追加や並べ替えは未実装。
なるべく、自分が使ってもストレス無く使えるようにしたい。普通に文字入力してる感覚でサクサク作れるようなのが理想だなあ。
LL魂 - Aug 05, 2007
Lightweight Language Spirit、通称LL魂行ってきましたよ。
前日朝までウトウトしながらテキストシャドウのコードいじってて(改行の問題の修正)、2~3時間寝た後昼過ぎくらいまでかけて必死こいてプレゼン資料作ってました。なのでVM魂より前の内容は見てません。しかもVM魂も会場で寝ちゃって最後の方の内容見れてません。酷い話だ。
amachangさんのプレゼンはさすがという感じで、JSだけでここまでやれる物なんだぁ……と、今更改めて驚かされました。サムネイルでプレゼン全体を一覧したりする機能(amachangさんのはプレゼンツールの機能として組み込んだものではないそうだけど)はそのうち是非ともパクらせていただきたい所存ではあります。というか会場の質問で「同じJS同士、コラボレーションやりますか」みたいな話が出てしまったので、その方向も含めて検討課題ですね。事務屋的というか地味なXULをamachangさんの協力で是非とも派手派手なものにしていただけたらなあとか思っています。
他はあまりに分野が違いすぎてコメントのしようがない……でもGaucheの小黒氏のプレゼンはなかなか興味深かった。最後の方ニコニコ的展開になってて、これがプレゼン2.0というやつか!みたいな。
そう。OHP由来のスライド型プレゼンの枠を乗り越えていないのが残念だったと言われたけれども、プレゼンっていうかパフォーマンス? 壇上で言語使ってPCとプロジェクター使って発表するという段階で自ずとそのフォーマットは限定されてくる物なのではないかと、僕なんかは思うわけですよ。しかもテーマが「その言語で作ったプレゼンツール」じゃないすか。そうしたらなおさら、形式は限定されて仕方のない話だと思うわけですよ。
リアルタイムに動かせたらそれでいいの? XULをその場で書いてそれがプレゼン内で表示される、そういう風にすればよかったの? でもその場でやってtypoで動かなかったら、制限時間内にプレゼンが終わらないかもしれない。伝えたかった事を伝えきれないかもしれない。「重要な事をあらかじめスライドに書いておいて、それをめくりながら話す」という「プレゼンテーション」の「形式」は、廃れることなく何十年と行われ続けてきている。これはもう、僕のようなボンクラな人間にとって、そしてボンクラが圧倒的多数を占めている人類という種にとって、この形式が一番「適している」のではないか? そんなことすら思ったりもするわけですよ。
次回予告。2008年8月30日、なかのZEROホール(収容人数1300人)。スケールでかいなあ……
以下、飲み会で話した事。
- Mozilla 24って結局なんなのかよく分からないから、技術者の間では話題にすら上らない。情報がちっとも出てこないから話題にしようがないんだよね。
- オープンソースのイベントとかっていうと、昔は同好会的雰囲気がメインだったけど、最近は、「起業! 起業!」って目がギラギラした人達が増えてきてつまんなくなったよね。
- userChrome.jsとかGreasemonkeyとかの方が人気で、拡張機能作者は冷や飯食い感があるですよ。でもAutoPagerizeは便利だ(飲み会の席ではPage Concaterと言っていたけど、AutoPagerizeの間違いでした。すみません)。
そんな感じ。